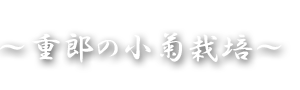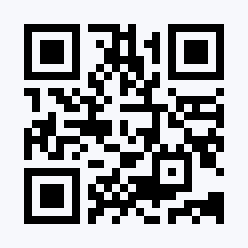小菊出荷が一段落した
2か月以上もブログを更新できなかった。
盆先の出荷を始めたのが7月22日で、以後週3回のペースで収穫調製と翌朝の箱詰め出荷を8月21日まで繰り返した。連日の猛暑だったのでLEDヘッドライトを点けて朝3時~4時半ころから収穫を始め、選花機にかけて水を張った桶に入れたら昼ごはん。昼寝を1~2時間して14時前後に作業を始め、22~23時ころに段ボール箱を作って終わり。翌朝は出荷量によるが4時前後に起きて箱詰めして6時半過ぎに出発して7時前に集荷・検査場に持ち込む。この繰り返しなので体重が落ちる。出荷日の夕方が防除や草刈りなど別の作業ができる時間になる。
お盆に少し休んで墓参りやBBQをした。
彼岸咲は9月7日から始め24日で終了した。㈱花満に出荷したのは、盆咲24千本、彼岸咲は17千本で、他に産直イベントやJA産直市へ3千本ほど出荷した。あと1週間もすると10月咲の出荷が始まるが、植付本数が多くないのと気候も良いので大きな負担ではない。一方で、自家繁殖の権利を持つ7品種を圃場から掘り出して整形してハウス内に植付ける作業や圃場の片付けと来年の準備が待っている。
今年の反省点はいろいろあるが、今回は価格のことを書いておく。
価格の推移グラフを見ると、R7年は春先から価格低迷で、盆前にやっと平年並みの価格が出現した。盆を過ぎるとまた下落して、彼岸前に上昇して彼岸を過ぎると下落。つまり需要期だけ価格が上がってそれ以外は20円~40円、10円台も出現と決して嬉しくない価格推移であった。物価高騰で仏壇の花を買う余裕がなくなっているのだろうか。スーパーの小菊3本束も以前は300円弱だったのが今年は400円弱になっている。
 選花機にかかけた菊をチェックしながら10本束にする風景
選花機にかかけた菊をチェックしながら10本束にする風景
 小菊の価格推移.pdf
小菊の価格推移.pdf
ご要望があったので最後に残ったマニュアル第9章と第10章を添付しておきます。
 出荷終了後のほ場の管理.pdf
出荷終了後のほ場の管理.pdf
 親株の植付と挿し穂の生産.pdf
親株の植付と挿し穂の生産.pdf
盆先の出荷を始めたのが7月22日で、以後週3回のペースで収穫調製と翌朝の箱詰め出荷を8月21日まで繰り返した。連日の猛暑だったのでLEDヘッドライトを点けて朝3時~4時半ころから収穫を始め、選花機にかけて水を張った桶に入れたら昼ごはん。昼寝を1~2時間して14時前後に作業を始め、22~23時ころに段ボール箱を作って終わり。翌朝は出荷量によるが4時前後に起きて箱詰めして6時半過ぎに出発して7時前に集荷・検査場に持ち込む。この繰り返しなので体重が落ちる。出荷日の夕方が防除や草刈りなど別の作業ができる時間になる。
お盆に少し休んで墓参りやBBQをした。
彼岸咲は9月7日から始め24日で終了した。㈱花満に出荷したのは、盆咲24千本、彼岸咲は17千本で、他に産直イベントやJA産直市へ3千本ほど出荷した。あと1週間もすると10月咲の出荷が始まるが、植付本数が多くないのと気候も良いので大きな負担ではない。一方で、自家繁殖の権利を持つ7品種を圃場から掘り出して整形してハウス内に植付ける作業や圃場の片付けと来年の準備が待っている。
今年の反省点はいろいろあるが、今回は価格のことを書いておく。
価格の推移グラフを見ると、R7年は春先から価格低迷で、盆前にやっと平年並みの価格が出現した。盆を過ぎるとまた下落して、彼岸前に上昇して彼岸を過ぎると下落。つまり需要期だけ価格が上がってそれ以外は20円~40円、10円台も出現と決して嬉しくない価格推移であった。物価高騰で仏壇の花を買う余裕がなくなっているのだろうか。スーパーの小菊3本束も以前は300円弱だったのが今年は400円弱になっている。
 選花機にかかけた菊をチェックしながら10本束にする風景
選花機にかかけた菊をチェックしながら10本束にする風景 小菊の価格推移.pdf
小菊の価格推移.pdfご要望があったので最後に残ったマニュアル第9章と第10章を添付しておきます。
 出荷終了後のほ場の管理.pdf
出荷終了後のほ場の管理.pdf 親株の植付と挿し穂の生産.pdf
親株の植付と挿し穂の生産.pdf水稲のこと
3枚計13アールの水田で自家用の水稲を作っている。3枚とも小菊栽培用に借りたのだが、条件が悪かった(内水洪水など)ので水稲にした。R6年は、814㎏の収穫があった。626㎏/10アールだから良い成績だと思う。これにかかった生産費は、肥料、農薬、苗代、乾燥調整代、燃料代、地代で86,461円。他に労賃(@2,000円)として畦畔草刈りと田植えなどで28時間、56,000円を加えると142461円になる。玄米1㎏あたり175円であった。
これに含まれていないのが農機具代と利益である。農機具代は、1年に1日しか使わない田植機とコンバイン、何回か使うトラクターが主なものだが、計上が難しい。というか、別収入がないと農機具を揃えられない。耕作面積1ヘクタール程度の稲作農家は、兼業農家という言葉があるように、別の稼ぎで農機具を揃えていたのではないか。
水稲栽培の利点は、連作障害がないこと(毎年同じ場所で作れる)と機械化が進んでいる(作業時間が少ない)ことである。草刈り以外の手作業はほとんどない。一方の畑作は、連作障害があるうえ手作業が多い。畑作に手を出す稲作農家はほとんどいない。小菊栽培も畑作で、自分自身、20アールの作業に限界を感じている。
農業の根本的な欠陥は農閑期と農繁期があることである。大型稲作農家は、農繁期に備えて従業員を揃え、農機具代を含む経営を経理しているのだろうが、農閑期の収入策(雇用対策)は大きな問題ではなかろうか。水稲単作経営は難しいのかな、などとかんがえばがら、5㎏4千円といった米騒動のテレビを見ています。
あと3週間もすれば盆咲の出荷が始まります。最盛期になると、晴天だと陽が登る前に切り取り(収穫)を終えたいので朝4時からヘッドライトを点けて始め、遅い朝食の後、選花機にかけて束作りして、夕食を食べて作業を続け伝票を作るのが23時頃になる。翌朝は5時頃から出荷用の箱詰めと検査所への持ち込みをやって8時頃に解放される、といった生活が8月10日ころまで続きます。
 収穫と出荷調製.pdf
収穫と出荷調製.pdf
 付表 出荷規格.pdf
付表 出荷規格.pdf
これに含まれていないのが農機具代と利益である。農機具代は、1年に1日しか使わない田植機とコンバイン、何回か使うトラクターが主なものだが、計上が難しい。というか、別収入がないと農機具を揃えられない。耕作面積1ヘクタール程度の稲作農家は、兼業農家という言葉があるように、別の稼ぎで農機具を揃えていたのではないか。
水稲栽培の利点は、連作障害がないこと(毎年同じ場所で作れる)と機械化が進んでいる(作業時間が少ない)ことである。草刈り以外の手作業はほとんどない。一方の畑作は、連作障害があるうえ手作業が多い。畑作に手を出す稲作農家はほとんどいない。小菊栽培も畑作で、自分自身、20アールの作業に限界を感じている。
農業の根本的な欠陥は農閑期と農繁期があることである。大型稲作農家は、農繁期に備えて従業員を揃え、農機具代を含む経営を経理しているのだろうが、農閑期の収入策(雇用対策)は大きな問題ではなかろうか。水稲単作経営は難しいのかな、などとかんがえばがら、5㎏4千円といった米騒動のテレビを見ています。
あと3週間もすれば盆咲の出荷が始まります。最盛期になると、晴天だと陽が登る前に切り取り(収穫)を終えたいので朝4時からヘッドライトを点けて始め、遅い朝食の後、選花機にかけて束作りして、夕食を食べて作業を続け伝票を作るのが23時頃になる。翌朝は5時頃から出荷用の箱詰めと検査所への持ち込みをやって8時頃に解放される、といった生活が8月10日ころまで続きます。
 収穫と出荷調製.pdf
収穫と出荷調製.pdf 付表 出荷規格.pdf
付表 出荷規格.pdfミルとモモ
猫の名前である。ミルは1991年頃に岡崎市細川町の古村積神社そばで長男が小学校帰りに拾ってきた。最初の名前はミルクで保育園に行っていた次女が付けたらしい。白と灰色の「藤ネコ」である。変だというのでミルに変わった。ミルは転勤族で、家族ともどもバングラデシュに転勤することになった時、広島の両親に預けた。父と農道を散歩する犬のような猫だったらしい。父が1996年に亡くなり、母が2005年に亡くなってからは私が引き取って、再び岡崎市、横浜市と移った。横浜では東日本大震災にも遭った。それから私の退職に併せて広島の両親が居た家に移って住むようになった。そこで2013年7月に死んだ。
モモは、1996年頃のバングラデシュ国ダッカ市生まれである。確か日本人学校の友達のところから中学生の長女がもらってきて、誰かが名前を付けた。白地のきれいな三毛猫で神経質だった。日本に連れて帰ることになって、当時は機内にカゴで持ち込めたが、中継地のバンコクではホテルに入ることはできず動物病院に1泊した。その後は家族と生活したが、家族がアパート住まいだったので鳴き声が外に漏れないよう、妻はずいぶん苦労した。モモも広島市内を何か所か引っ越ししている。子供たちが就学や就職や結婚して妻のところから離れていった。私は単身赴任していた。最後は妻との生活になったが、妻の友人が預かってくれることになり、そこで何年かその家族として生活した。
私たちが退職して広島の実家に住むようになって、しばらくして具合が悪くなり、妻が引き取りに行った。実家に着いた時、モモは車の後部座席で死んでいた。2013年10月だった。
2匹は、それぞれ木箱に入れて、家の前の桜色の花をつけるハナミズキの下に埋めた。ハナミズキは、2匹の養分を少しもらって育ったハズなので、”生まれ代わり”と思っている。

約1か月振りである。これまで忙しかったし今も忙しいが、幸いに今日は梅雨空で、彼岸咲の整枝作業は中断。ブログに向き合うことができた。今回は、内容が複雑な「防除」関係のマニュアルと関係資料をアップします。
 防除マニュアル.pdf
防除マニュアル.pdf
 使用薬剤一覧表.pdf
使用薬剤一覧表.pdf
 防除の考え方.pdf
防除の考え方.pdf
モモは、1996年頃のバングラデシュ国ダッカ市生まれである。確か日本人学校の友達のところから中学生の長女がもらってきて、誰かが名前を付けた。白地のきれいな三毛猫で神経質だった。日本に連れて帰ることになって、当時は機内にカゴで持ち込めたが、中継地のバンコクではホテルに入ることはできず動物病院に1泊した。その後は家族と生活したが、家族がアパート住まいだったので鳴き声が外に漏れないよう、妻はずいぶん苦労した。モモも広島市内を何か所か引っ越ししている。子供たちが就学や就職や結婚して妻のところから離れていった。私は単身赴任していた。最後は妻との生活になったが、妻の友人が預かってくれることになり、そこで何年かその家族として生活した。
私たちが退職して広島の実家に住むようになって、しばらくして具合が悪くなり、妻が引き取りに行った。実家に着いた時、モモは車の後部座席で死んでいた。2013年10月だった。
2匹は、それぞれ木箱に入れて、家の前の桜色の花をつけるハナミズキの下に埋めた。ハナミズキは、2匹の養分を少しもらって育ったハズなので、”生まれ代わり”と思っている。

約1か月振りである。これまで忙しかったし今も忙しいが、幸いに今日は梅雨空で、彼岸咲の整枝作業は中断。ブログに向き合うことができた。今回は、内容が複雑な「防除」関係のマニュアルと関係資料をアップします。
 防除マニュアル.pdf
防除マニュアル.pdf 使用薬剤一覧表.pdf
使用薬剤一覧表.pdf 防除の考え方.pdf
防除の考え方.pdf菊栽培作業が本格化!
4月30日から盆咲の電照を始めた。約10アールの圃場に70個余りのLED電球を取り付け、夜10時から翌朝3時半まで点灯する。近所には申し訳ないが、"きれい"と言ってくれる人もいる。6月中旬まで続け、フル稼働の5月分の電気代は4千円くらい。
今日5月11日に初めての防除をした。薬液80㍑で約1時間の作業で済んだが、この作業、成長に伴って薬量と散布にかかる時間が増えてくる。次回は14日、だいたい10日に2回の間隔で、多種類の薬剤を組み合わせてターゲットの害虫や病害を予防しようと頑張るが、時に病害虫が上手だったりする。
彼岸咲の定植もあと4日後に始まり、約7,500本を植える。残るは10月咲の5千本、あと1か月先のこと。
盆咲の成長が早い品種は、25㎝くらいの丈に育っていて、1週間もすれば整枝作業を始める。ひと株ずつ進めるので時間がかかり、背中と腰が痛くなる。
これに加わるのが稲作と草刈り。稲作は3枚の田んぼで13アール、菊を作ろうと借りたのが内水洪水で使えず、自家用のコメ作りに変えたもの。草刈は、自宅周辺だけでなく地域内の水路法面などを皆で共同で刈る。ほぼ2週間ごとの週末の作業になる。
楽しみは夕食前のビール!
今回は、マニュアルを2つ添付しましょう。
 第4章 開花調整の方法.pdf
第4章 開花調整の方法.pdf
 第5章 整枝の方法.pdf
第5章 整枝の方法.pdf

今日5月11日に初めての防除をした。薬液80㍑で約1時間の作業で済んだが、この作業、成長に伴って薬量と散布にかかる時間が増えてくる。次回は14日、だいたい10日に2回の間隔で、多種類の薬剤を組み合わせてターゲットの害虫や病害を予防しようと頑張るが、時に病害虫が上手だったりする。
彼岸咲の定植もあと4日後に始まり、約7,500本を植える。残るは10月咲の5千本、あと1か月先のこと。
盆咲の成長が早い品種は、25㎝くらいの丈に育っていて、1週間もすれば整枝作業を始める。ひと株ずつ進めるので時間がかかり、背中と腰が痛くなる。
これに加わるのが稲作と草刈り。稲作は3枚の田んぼで13アール、菊を作ろうと借りたのが内水洪水で使えず、自家用のコメ作りに変えたもの。草刈は、自宅周辺だけでなく地域内の水路法面などを皆で共同で刈る。ほぼ2週間ごとの週末の作業になる。
楽しみは夕食前のビール!
今回は、マニュアルを2つ添付しましょう。
 第4章 開花調整の方法.pdf
第4章 開花調整の方法.pdf 第5章 整枝の方法.pdf
第5章 整枝の方法.pdf
日本語スピコン
長い寒波が続いたので、小菊の作業が無くなった。ハウス内の親株に白サビ病が入っていないか、今のところ感染なし。水平な畝を作るため圃場の平らさを測りたいが、土が湿っていてできない。確定申告(青色申告)で必要なレシート類のデータ入力は、手につかない。
そんな中、この日曜日に知人の誘いで日本語スピーチコンテストに行った。15人の外国人(留学生や実習生)が5分以内で話して、分かりやすさや内容などを審査して表彰する仕組み。主催は市の国際交流協会、後援が市や教育委員会に新聞社。会場は100人弱が詰めかけ熱気があった。感心したのは、大きな環境変化の中で暮らす発表者の話の内容がとても「前向きな人生」だったこと。”やばい”でごまかす我々と少し違うような気がした。
今回はマニュアル第3章「圃場準備と定植」をアップします。
 第3章 ほ場準備と定植.pdf
第3章 ほ場準備と定植.pdf

そんな中、この日曜日に知人の誘いで日本語スピーチコンテストに行った。15人の外国人(留学生や実習生)が5分以内で話して、分かりやすさや内容などを審査して表彰する仕組み。主催は市の国際交流協会、後援が市や教育委員会に新聞社。会場は100人弱が詰めかけ熱気があった。感心したのは、大きな環境変化の中で暮らす発表者の話の内容がとても「前向きな人生」だったこと。”やばい”でごまかす我々と少し違うような気がした。
今回はマニュアル第3章「圃場準備と定植」をアップします。
 第3章 ほ場準備と定植.pdf
第3章 ほ場準備と定植.pdf
親株の育成中
写真はハウス内で育成中の親株です。幅5m長さ15mのハウスの3ウネに7品種2,800株の親株を植えている。
植えたのは去年の11月半ば。秋祭りの当番に当たったので普段より半月遅れ。親株は、出荷して残った株を掘り起こして整形したもの。幅90㎝長さ13mのウネに1千本弱植えている。7品種全てが種苗会社の承諾(許諾料を支払い)を得ている。そうでないと種苗会社から訴えられる。小菊生産にも種苗法という規制があるのです。
2月20日を過ぎると気温が上がってきて芽が伸びてくる。伸びた芽を上から8㎝折り取って(これを「穂」という)挿し穂し、約3週間かけて発根させてからほ場に定植します。お盆向けには3月15日ころ、彼岸用には4月28日ころに穂を採って、4月4日ころと5月18日ころに定植する予定です。このハウスから約8千本の穂を採取する計画です。
今回は、マニュアル第2章「挿し穂と育苗」を添付します。
 第2章 挿し穂と育苗.pdf
第2章 挿し穂と育苗.pdf
 中央に灌水チューブ 地面が割れて芽が出ている
中央に灌水チューブ 地面が割れて芽が出ている
植えたのは去年の11月半ば。秋祭りの当番に当たったので普段より半月遅れ。親株は、出荷して残った株を掘り起こして整形したもの。幅90㎝長さ13mのウネに1千本弱植えている。7品種全てが種苗会社の承諾(許諾料を支払い)を得ている。そうでないと種苗会社から訴えられる。小菊生産にも種苗法という規制があるのです。
2月20日を過ぎると気温が上がってきて芽が伸びてくる。伸びた芽を上から8㎝折り取って(これを「穂」という)挿し穂し、約3週間かけて発根させてからほ場に定植します。お盆向けには3月15日ころ、彼岸用には4月28日ころに穂を採って、4月4日ころと5月18日ころに定植する予定です。このハウスから約8千本の穂を採取する計画です。
今回は、マニュアル第2章「挿し穂と育苗」を添付します。
 第2章 挿し穂と育苗.pdf
第2章 挿し穂と育苗.pdf 中央に灌水チューブ 地面が割れて芽が出ている
中央に灌水チューブ 地面が割れて芽が出ている